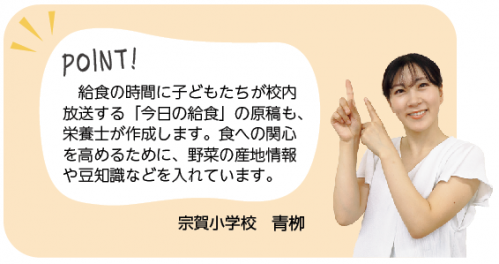本文
1時間目 学校栄養士のお仕事
どんな仕事しているの?
学校栄養士は普段どんな仕事をしているのか。栄養士のインタビューと共に、さまざまな業務がある中でも、重要な仕事の一部をご紹介します。
やりがいは、子どもたちの喜ぶ笑顔
 学校栄養士の大切な仕事の一つに「食育」があります。私が食育で心掛けていることは、こちらが一方的に話すだけでなく、子どもたちが興味や関心を持ち自ら考えられるような内容にすることです。野菜の生産者をお呼びして話をしてもらったり、給食で出すトビウオの実物を見せてみたり、子どもたちの記憶に少しでも残るような食育を目指しています。
学校栄養士の大切な仕事の一つに「食育」があります。私が食育で心掛けていることは、こちらが一方的に話すだけでなく、子どもたちが興味や関心を持ち自ら考えられるような内容にすることです。野菜の生産者をお呼びして話をしてもらったり、給食で出すトビウオの実物を見せてみたり、子どもたちの記憶に少しでも残るような食育を目指しています。
自校給食で学校に栄養士や調理員がいるためか、本校には食への興味や関心が高い子どもが多いなと感じています。学校給食は生きた教材でもあるので、子どもたちが楽しみながら「食」について学ぶ場になってくれたらうれしいですね。今後は、ALT(外国語指導助手)の故郷の料理や、品種違いの野菜の食べ比べなどを給食で取り入れてみようと計画中です。
新しいメニューを考える時は、いろいろな料理を食べてみたり、周りの人たちの作っている料理や子どもからの意見を参考にしたりしています。考えたメニューは、実際に家で試作してから提供しています。自校給食は、子どもたちの素直な反応を目の前で見て、感想などを直接聞けるので、それが一番のやりがいになっていますね。
子どもたちの力になる給食を
物価高騰の影響で、食材は年々値上がりしています。今後も物価が上がる可能性を考えながら、予算内で献立を作らなければいけません。その中でも、地場産食材を積極的に活用しながら、栄養価を落とさずに子どもたちの力になる給食を提供していきたいです。
旬と地場産食材を取り入れたこだわりの食材発注
 学校給食で使用する野菜などは、できるだけ地場産の物を使うようにしています。時期によって採れる物が違うので、卸売業者や地元農家さんにどの時期に市内産が出るかなどの情報提供をしてもらっています。発注時も市内産の物を指定するなど、地産地消を意識しています。
学校給食で使用する野菜などは、できるだけ地場産の物を使うようにしています。時期によって採れる物が違うので、卸売業者や地元農家さんにどの時期に市内産が出るかなどの情報提供をしてもらっています。発注時も市内産の物を指定するなど、地産地消を意識しています。
子どもたちに、今の季節はどの野菜がおいしいのかなど旬を感じてほしいので、旬の物は必ず出すように心掛けています。
つながりを大切に、地産地消を後押し
 学校に納品する野菜などの生産者を選ぶときは、生産者のお孫さんがいればその学校に提供できるように意識するなど、つながりを大切にしています。それも食育につながると思うので。これからも、地産地消を推進する塩尻市の学校給食を、影ながらサポートしていきます。
学校に納品する野菜などの生産者を選ぶときは、生産者のお孫さんがいればその学校に提供できるように意識するなど、つながりを大切にしています。それも食育につながると思うので。これからも、地産地消を推進する塩尻市の学校給食を、影ながらサポートしていきます。
法律で決められている!? 献立作り
 栄養士が一番大切にしている献立作成。本市では、栄養計算ソフトを用いて献立作成をしています。食品を選択すると栄養価を自動で計算してくれる優れものです。
栄養士が一番大切にしている献立作成。本市では、栄養計算ソフトを用いて献立作成をしています。食品を選択すると栄養価を自動で計算してくれる優れものです。
献立は好きなものを自由に組み合わせれば良いというわけではなく、学校給食法という法律で目標が決められており、その他にもポイント(下記参照)があります。給食調理員の数や釜の数も限られているので、調理方法が偏らない、かつ時間内に完成させられるものでなければいけません。物価が高騰していますが、なんとか予算を超えずに子どもたちにしっかりと食べてもらえるような工夫をして献立を作っています。献立は学校ごとに作るので、学校行事に合わせるなどの工夫もできます。
献立作成のポイント
○各校で算出した給与栄養目標量の栄養素基準を満たしているか
○予算内に収まるか
○調理ルールを守った上で作れるか
○地場産食材や旬の食材は使われているか
○揚げる・炒めるなどの調理方法や、味付けが連続または重複しないようにバランスが取れているか
○行事などに合わせた食事になっているか
○国が定める学校給食衛生管理基準に基づいているか
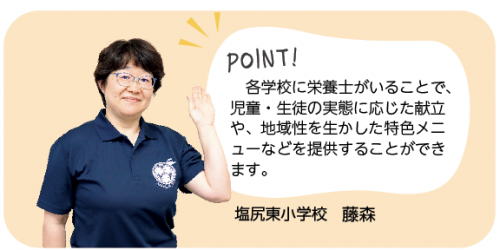
気を抜けない食物アレルギー対応
 食物アレルギーは、一歩間違えると命に関わる重大な事故につながります。そのため、学校では医師に書いてもらった書類を基に、食物アレルギーのある子どもの保護者と毎年面談を行います。面談でアレルギー症状の確認や緊急時の対応を検討し、対応の可否を決定します。
食物アレルギーは、一歩間違えると命に関わる重大な事故につながります。そのため、学校では医師に書いてもらった書類を基に、食物アレルギーのある子どもの保護者と毎年面談を行います。面談でアレルギー症状の確認や緊急時の対応を検討し、対応の可否を決定します。
対応食を提供する子どもの家庭には、通常の献立表とは別に、代替品名や何が入っているかなどを記載した食物アレルギー用の献立表を事前に確認してもらいます。発注時も、「卵不使用マヨネーズ」など細かく品目を指定し、原材料を確認しています。また、調理中は専用エプロンを着用し、給食提供までに複数回のチェックをしています。
食の大切さを伝える食育の伝道師
食育の一環で、教室に出向き食育の授業をすることもあります。運動会の練習が始まって体を動かす授業が増えてくる時期には、「朝食の大切さ」について給食時に話をしました。手作りの教材を用いて子どもたちの興味を引き、朝食を食べることで朝から元気に過ごせることを、分かりやすく伝えました。

豆知識たっぷり食育だより作成
 学校ごと月に1・2回発行している食育だより。月の給食目標に合わせて、その時期に伝えたいことや豆知識をイラストなどを交えて分かりやすく伝えています。また、予定献立表では、その日の給食のポイントや思いを伝える一口メモが記されている学校もあります。
学校ごと月に1・2回発行している食育だより。月の給食目標に合わせて、その時期に伝えたいことや豆知識をイラストなどを交えて分かりやすく伝えています。また、予定献立表では、その日の給食のポイントや思いを伝える一口メモが記されている学校もあります。